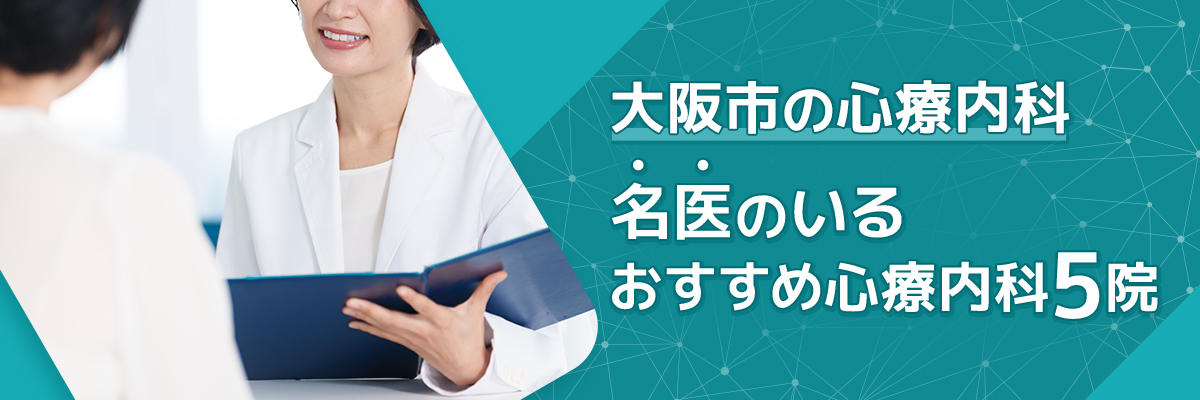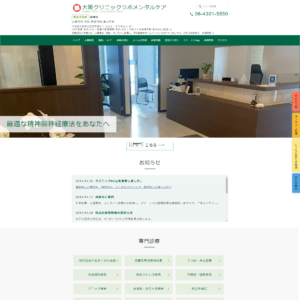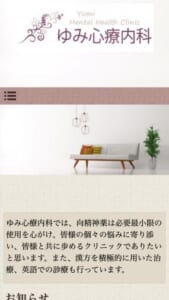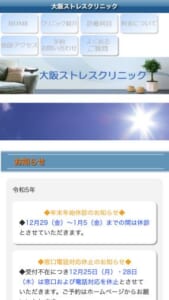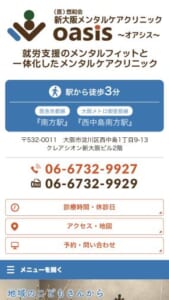薬物療法の詳細な診療内容
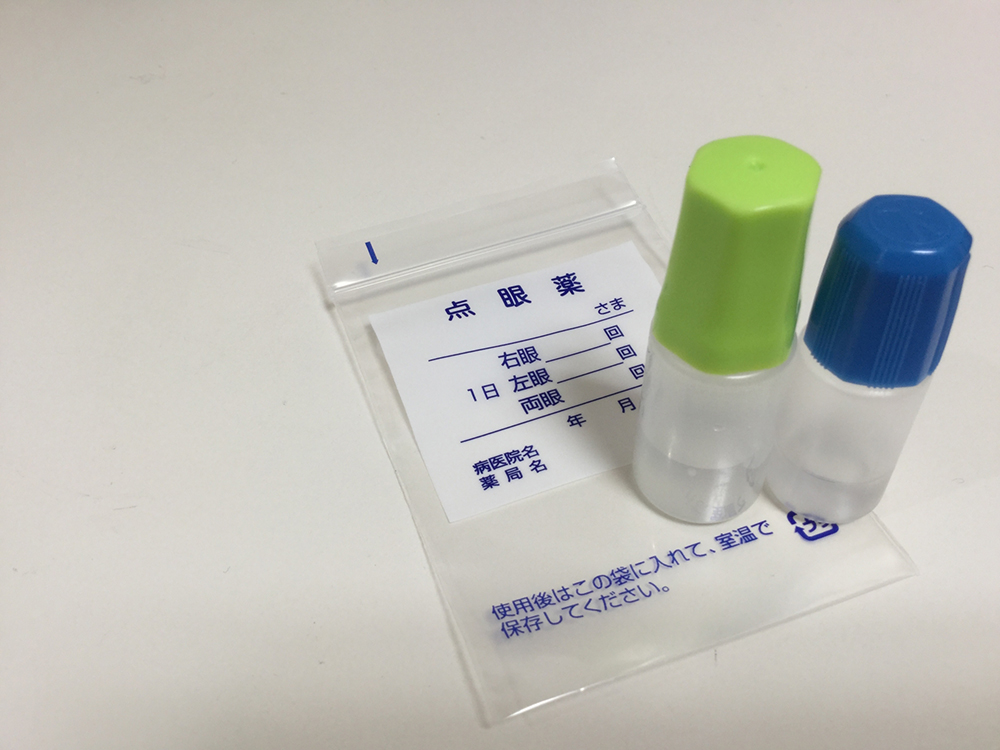
適応症と薬物治療の基本的なメカニズム
薬物療法は心療内科において広く使用される治療法の一つであり、適応症と治療の基本的なメカニズムを理解することは重要です。まず、薬物療法は主にうつ病や不安障害、統合失調症などの精神疾患に対して適用されます。これらの疾患には脳内の神経伝達物質のバランスが崩れていることが関与しており、薬物療法はこのバランスを修復することを目指しています。
適応症において、薬物療法は特定の神経伝達物質に作用することで症状の改善を図ります。例えば、うつ病の場合、セロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質の不足が考えられ、抗うつ薬はこれらの物質の再取り込みを阻害することで効果を発揮します。同様に、不安障害に対しては抑制神経伝達物質の増加を促すことで症状を緩和させます。これにより、神経伝達物質のバランスが回復し、患者の症状が改善されるのです。
薬物療法の効果と副作用に関する情報
薬物療法の効果と副作用に関する情報を正しく理解することは、治療の進行や患者の安全性を確保する上で不可欠です。まず、薬物療法の効果は個人差があります。同じ薬物を使用しても、患者の生理学的な特徴や症状の種類によって効果が異なることがあります。効果が現れるまでには時間がかかることもあるため、患者と医師は協力して適切な期待値を持ちながら治療を進める必要があります。
一方で、薬物療法には副作用が伴うことがあります。これらの副作用は薬物の種類や患者の個別の反応によって異なります。一般的な副作用には吐き気、めまい、食欲の変化などが含まれますが、これらは通常短期的で軽度です。ただし、重篤な副作用もあるため、患者は医師に定期的に状態を報告し、必要に応じて調整を行うことが大切です。
カスタマイズされた薬物治療の進め方
薬物療法の進め方は患者の個別性を考慮したカスタマイズが不可欠です。まず、治療開始前に医師は患者の病歴や現在の症状、生活状況などを詳細に把握します。これによって、最適な薬物の選択や適切な投与量を決定する基盤が構築されます。
また、治療の進行中も患者の状態に応じて薬物の調整が行われます。患者の反応や副作用の発現、症状の変化などを継続的にモニタリングし、必要に応じて治療計画を変更することで、最良の結果を得ることが期待されます。この過程で患者と医師との密なコミュニケーションが重要であり、患者が治療に対して納得感を持ちながら進めていけるように工夫されています。
カスタマイズされた薬物治療の進め方は、患者が最も効果的かつ安全に治療を受けるための手法であり、個別のニーズや要望を的確に反映させることが期待されます。